
共創の最前線で生まれるストーリーから
次なるオープンイノベーションの可能性を紐解く。
ISTORY
#01
HIROTSUバイオサイエンスの挑戦
「世界初のサイエンス」を「世界初のビジネス」へ
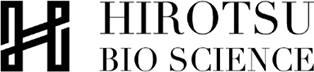

湘南R&Dセンター長 エリック・デルクシオ氏
株式会社HIROTSUバイオサイエンス
- 2016年
- 設立
- 2020年
- 世界初の線虫を活用したがんの一次スクリーニング検査「N-NOSE®」を実用化。
湘南アイパークに研究拠点「湘南R&Dセンター」を移転開設。
- 2021年
- すい臓がんの特定が可能な特殊線虫の開発に成功
評価額1,000億円を突破し、日本のヘルスケア分野初のユニコーン企業となる。
- 2022年
- 世界初の早期すい臓がん検査「N-NOSE® plus すい臓」を実用化
現在、研究メンバーは13名
フランス・イラク・タイなど世界から集まったグローバルなチームで研究を進める
エリック・デルクシオ(Eric Di Luccio)
- 2003年
- 地中海エクスマルセイユII大学院大学(フランス)にて神経科学構造生物学専攻、理学博士号を取得
カリフォルニア大学デイビス校(アメリカ)分子生物学部及びコンピューターサイエンス学部にて研究員。
- 2010年
- 慶北大学(韓国)にて助教授、その後准教授として、がんの研究に携わる
- 2020年
- 株式会社HIROTSUバイオサイエンス入社。湘南R&Dセンター長着任。
- 2022年
- 株式会社HIROTSUバイオサイエンス執行役員、技術最高責任者(CTO)に就任。
尿1滴で全身15種類の早期がんを検知する
世界初“線虫がん検査”










